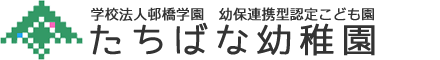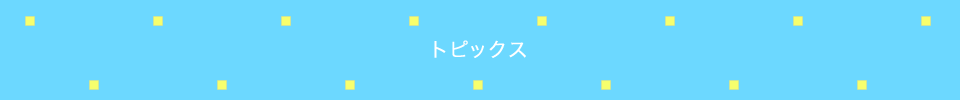| Number | |
|---|---|
| 投稿年月日 | |
| 題名 | |
| 内容 | |
| 投稿者 |
5月巻頭言 中国からの見学者
先日、中国からの見学者が幼稚園に来られました。私が非常勤講師としてお世話になっている大学のつながりで、昨年度もいらっしゃいましたが、今回は前回とは違い、中国の園長先生が多く参加された見学でした。前回の見学では、乳児の子どもたちが自ら静かに食べている様子に、中国の方々が驚いていました。中国では、乳児期の子どもは祖父母が世話をするのが一般的で、子どもに食べさせることも多く、自ら食べる機会は少ないそうです。そのため、幼稚園の子どもたちの様子はかなり衝撃的だったようです。また、幼稚園を紹介したYouTube動画は300万回以上再生され、中国でも大きな反響があったそうです。
こうしたこともあり、今回改めて中国の方々が見学に訪れました。今回は乳児保育だけでなく、幼児保育の様子も見学し、特に注目された点が印象的でした。それは「保育者の情緒の安定」と「子どもの自立性」です。これを感じたのは、相撲の様子からだったそうです。芝生の上にマットを円状に敷いて、子どもたちが相撲をしていました。こうしたコンタクトスポーツは、中国ではあまり行わないようです。見学中に相撲中にちょっとしたトラブルが起きました。負けて悔しくて泣く子や、転んで泣いてしまう子などがいたのですが、その際、先生はトラブルにすぐに介入するのではなく、「大丈夫?」「こっち来る?」といった寄り添う言葉をかけていました。それに対し、子どもたちは自ら立ち上がって再開する子もいれば、先生のそばに座る子もいました。この様子に、中国の方々は驚いていたようです。聞くところによると、中国ではケガに対して非常に敏感で、少しのケガでもクレームが来るそうです。そのため、保育者は子どもの関わりに対して非常に敏感に対応する必要があるとのことでした。そうした背景もあり、今回の見学で保育者が落ち着いた柔らかな表情で子どもたちに関わっている姿に驚かれたようです。
「なぜ、こんなにも保育者が落ち着いているのか?」という質問に対して、私は「子どもたちが必要なときに必要な関わりをしているからで、助けがいるかどうかも子どもたち自身が決めている。それは自立のために必要なことであり、保育者はそのために子どもとの距離感を大切にしている」と説明しました。保育者がすべてを世話するのではなく、必要なときに対応できる距離感や安心感が大切だと思っています。もちろん、トラブルで手が出てしまうことや大きなケガが起きないように、未然に防ぐための距離感が求められます。しかし、自分で対応できることは自分たちで解決できるように支援しなければいけません。そのため、子どもたちの様子を観察しながら距離感を調整しています。このような関わり方を通して、子ども自身が経験することが保障され、自立が促されるのだと思います。
こうした園で大切にしていることを、見学を通して伝わったことや、その価値を感じてもらえたことは、私たちにとっても自信につながる経験となりますし、異文化での感じ方や考え方は私たちにとっても勉強になります。
2025年5月7日