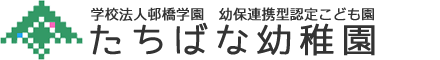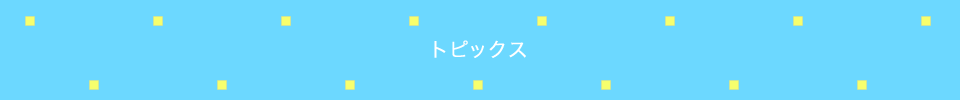| タイトル | |
|---|---|
| 内容 | |
| 投稿日時 |
7月巻頭言 いたずらと科学
先日、園内研修で「いたずら」について話す機会がありました。研修の中心は、今注目されている「STEM教育」の中の科学遊びについてでしたが、そのなかで「科学とは何か?」という話題になりました。
「科学」と聞くと、理科の実験や公式など、難しそうなものを思い浮かべるかもしれません。しかし、あるSTEM教育の本にはこう書かれています。「科学とは、観察・観測・実験結果をもとに法則性を見つけることです。」一見すると難しそうですが、要するに「やってみて、その結果を見て、なぜそうなったのかを考える」——この一連の流れこそが“科学”だといえるのではないでしょうか。そして、そのはじまりには、子どもたちの「どうなるんだろう?」「不思議だな」という小さな興味や疑問があるのです。
ここで、冒頭の「いたずら」の話に戻ります。「いたずら」は、大人にとっては頭を悩ませることも多く、「やってほしくないこと」として扱われがちです。ですが、子どもにとっては、それが好奇心から始まった“実験”なのかもしれません。もちろん、「迷惑なことは迷惑だよ」と伝えることは必要です。ただし、それと同時に、その行動の背景にある「やってみたい」という気持ちを受け止めてあげることも大切です。子どもたちの好奇心を否定せず、「やってもいい環境」をつくっていくこと。それこそが、私たち保育者の役割ではないでしょうか。思い切って試すことのできる「遊びの場」「実験の場」があることで、子どもたちはもっと自由に、のびのびと探究することができます。好奇心や学びの芽が、そこから大きく育っていくのです。
このような姿を考えている中で、10年ほど前、ドイツの保育現場を見学した際のことが思い出されます。現地の保育者たちは、乳児のことを「小さな科学者」と呼んでいました。乳児の部屋にはさまざまなおもちゃが用意されており、子どもたちはそれを手に取り、握ったり、投げたり、なめたり、見つめたりしていました。大人には何気ない行動に見えるかもしれませんが、それはすべて、自分の手で世界を知ろうとする「実験」です。赤ちゃんは大人よりもずっと強い好奇心を持ち、毎日たくさんのことを試しています。まさに彼らは、日々の生活の中で「科学」しているのです。
子どもたちの遊びをどのように見ていくかによって、保育の姿勢も変わります。たとえただ遊んでいるように見えても、その背景には深い学びがあるかもしれません。そして、その学びの芽を見逃さず、広げられるような環境を整えること。それが、子どもたちの可能性を引き出す保育につながっていくと私は考えています。
2025年7月7日