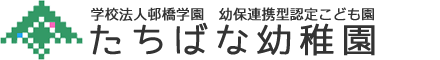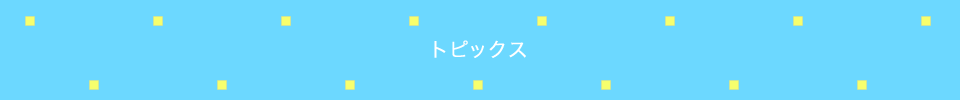| タイトル | |
|---|---|
| 内容 | |
| 投稿日時 |
6月巻頭言 主体性
最近、さまざまなところで保育の話をする機会が多くありました。その中でも、よく話の中心になる言葉が「子どもの主体性」です。この言葉は、保育をするうえで先生によって解釈が異なるものでもあります。そもそも「主体性」とは何をもってそう呼ぶのでしょうか。
「主体性」を辞書で調べてみると「自分の意志・判断で行動しようとする態度」とあります。AIに聞いてみると、「自分の意志や判断にもとづき、自ら責任をもって行動すること」と書かれていました。さらに、「仕事においては目的や課題を自ら設定し、その実現に向けて行動し、結果に責任を持つことを指す」とも答えていました。辞書よりも少し具体的に説明されていますね。一方で、これと似た意味で使われる「自主性」という言葉は「決められたことや指示されたことを率先して行動する力」であり、「決められた範囲で自発的に行動する力」を指しているようです。こうして比べてみると現在の保育や教育現場では「自主性」を子どもたちに求めていることが多いように思います。この言葉を通じてどのように考えるか、私自身も保育をするうえで、「主体性」をどのように保障するかを考えなければなりません。
保育においても、「一斉保育」(保育士が明確な目標をもって、子どもたちが集団で同じ活動を行う)か「自由保育」(子どもたちが自分の興味や好奇心にもとづいて、大人の指示やルールに縛られず、自ら遊びを選んで行動する)か、どちらが大事かという議論がありますが、私は「どちらも大事」だと思っています。バランスの問題で、子どもたちの発達にとっては、どちらにも意味や意図があるからです。しかし、より重要なのは「自由遊び」だと考えています。子どもたちは自ら選択し、興味・関心をもって遊びに取り組むからこそ、発達が促されます。そのため保育においては子どもたちが遊ぶ環境が重要だとされています。たちばな幼稚園が子どもたちの自由に遊ぶ環境を重視した保育を行っているのは、こうした理由からです。では、一斉保育にはどのような役割があるのでしょうか。
保育において、一斉保育の必要性は、「子どもたちに遊びの方法やルール、遊び方の提案やきっかけ」を与えることにあると考えています。つまり、自由遊びを充実させるために、一斉保育は重要なのです。たとえば、製作活動においては、「作品を作ること」が目的ではなく、「製作活動そのもの」が目的となります。いくら子どもたちに好奇心や探求心があっても、使い方やルールがわからないと遊べませんし、ケガのリスクもあります。子どもたちをただ放っておいても、氷おにが自然に始まることはありません。また、子どもたちが主体的に遊ぶ際、保育者の姿勢として大切なのが「引く」ということです。子ども同士で遊び始めたら、子どもたちが自ら遊ぶように、大人は「引いていく」ことが重要です。子どもたちが自ら関わりながら探求する活動では時に大人の存在が邪魔をしてしまうことがあります。大人が入るよりも子ども同士での関わりを重視した方がより活動はクリエイティブなものになります。自ら主体的に経験する中でこそ、「自分の意志や判断にもとづき、自ら責任をもって行動すること」に繋がります。そして、遊びの中でトラブルなどの関わりを通じて人間関係や人間性を深める経験をしていきます。
このように主体性な遊びが遂げられることで、子どもたちの発達は促され、非認知能力など、これから必要な力を培っていくことができると考えています。
2025年6月7日