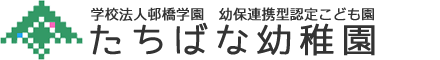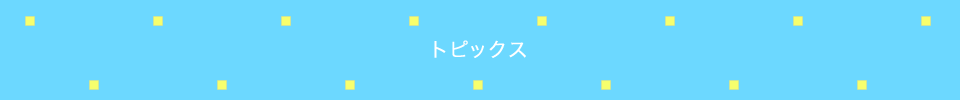| タイトル | |
|---|---|
| 内容 | |
| 投稿日時 |
10月巻頭言 本質
先日、門真市の教職員フォーラムに参加しました。これは市内の全小中学校の教職員と保護者が参加するイベントで、宮本市長の開会のあいさつや、教育委員会による取組みの説明、記念講演、参加者どうしの対話・交流などが行われました。一般市民も申し込めば参加できる形式であったため、私も参加させていただきましたが、今後の門真市の教育が大きく変わろうとしていることを実感できる、貴重な機会となりました。
門真市では現在、自由進度学習などを取り入れ、子どもたちが主体的に学べる環境づくりを進めています。教育変革はさらに加速していくと語られていましたが、一方で小学校には教科書やカリキュラムに沿った進度の制約があるため、授業を子ども主体に任せることには難しさもあるようです。こうした背景を踏まえ、記念講演では「そもそも教育は何のために行うのか」という問いが投げかけられました。
講師は熊本大学の苫野一徳先生です。教育者であり哲学者でもある苫野先生は、「教育を考えるには哲学が不可欠である」と強調されていました。実際、「教育とは何のために」という問い自体が哲学的なものだからです。私自身も、藤森メソッドを提唱された藤森平司先生から「保育は哲学として考えなければならない」と言われたことがあり、その言葉を思い出しました。社会の中で学校へ通う意味が問い直され、学歴や成績ばかりが人を測る基準となっている現状に、本当にそれでよいのかと改めて考えさせられます。生成AIの進歩も、学校の役割を揺さぶる要因になるでしょう。
苫野先生は「学校は何のためにあるのか」という問いに答える中で、ルソーの著作『エミール』を引用されました。「『あれしなさい、これしなさい、あれするな、これするな』とばかり言われて育った子どもは、そのうち『息をしなさい』と言われなければ呼吸さえしなくなるだろう」
極端な表現ですが、指示ばかりの環境では子どもが自ら考える力を失ってしまうことを鋭く表しています。最近耳にする「指示待ち人間」という言葉も、まさにその延長にあるのかもしれません。大人がよかれと思って与える指示が、子どもの可能性を奪ってしまうことは少なくないのだと思います。
現在、たちばな幼稚園では選択制や子ども同士の関わり、子どもに問いかけて一緒に考えることを大切にしています。これはまさに講演で語られた理念と重なるものであり、自分たちの取り組みの方向性を再確認することができました。確かに学歴や成績は依然として社会的に必要とされるスキルではあります。しかし、それ以上に本来の「保育」や「教育」の目的を見失わず、日々の実践に向き合うことが重要だと、改めて強く感じました。
2025年10月7日