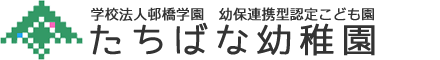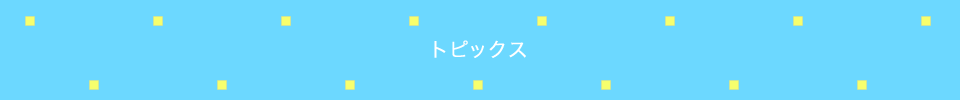| タイトル | |
|---|---|
| 内容 | |
| 投稿日時 | 2024年11月 |
| Number | |
| 投稿年月日 | |
| 題名 | |
| 投稿者 |
2024年11月 不適切保育を通して
不適切保育の話が最近もニュースで出ていました。こういった保育園のネガティブなニュースがたびたび放送され、保育に対する信頼性と安心感に不安を感じさせるものばかりが多いように感じます。改めて、乳幼児教育というのはどういったことが求められているのか、どういったことを保育として行っていかなければいけないのかを考えさせられます。
幼保連携型認定こども教育・保育要領には保育者は子どもにとって「信頼関係を十分に築き、園児が自ら安心して身近な環境に主体的に関わり、環境とのかかわり方や意味に気づき、これらを取り込もうとして、試行錯誤したり、考えたりするようになる幼児期の教育における見方や考え方を生かし、その活動が豊かに展開されるよう環境を整え、園児とともによりよい教育及び保育の環境を創造するよう努めるものとする」とあります。こう読んでいくと環境の創造にこそ保育者の役割があるということがわかります。そして、その環境では子どもは「主体的」であることが重要になってきます。
そう考えるとこれまでの様々な不適切保育の根底にあるものは、子どもの主体性というよりは保育者が指示することが主だった子どもが受容的な環境で起きる問題が多いように思います。私は常々「保育は指導ではなく、支援だ」と感じています。それは子どもたちの主体的な姿を保障するためには指示・指導ではなく、子どもたちの考えや活動を支援することの方が適しているからと考えているからです。
藤森メソッド(見守る保育)には「見守る三省」といった言葉があります。子どもたちに向かってどうあるべきかを日々省みるためにあるのですが、その一つ目に「子どもを丸ごと信じただろうか」とあります。そこには子どもは「自ら育とうとする力を持っている」ということを信じることから始まります。そして、二つ目に「子どもに真心をもって接しただろうか」とあります。それは子どもの育つ力を信じているからこそ、偽りのない心で子どもを主体として接することができるからです。それができると子どもたちは自分たちで活動していくので子どもを見守ることのほうがより主体的になります。なので、三つ目は「子どもを見守ることができただろうか」というように締められています。今紹介した内容は省略して紹介していますが、各部屋にこのことは掲示していますので、ぜひ一度ごらんください。
子ども自らの成長を信じ見守ることで子どもが主体的に得た成長や発達は指示・指導された姿より感動を得られ、自己肯定感にもつながります。そんな子どもたちの姿を保育者とも保護者の方とも共有できる幼稚園でありたいと改めて感じました。
2024年11月6日