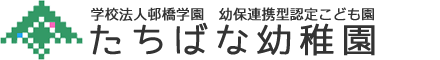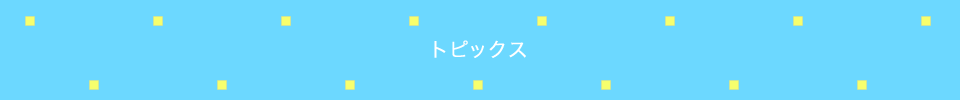| Number | |
|---|---|
| 投稿年月日 | |
| 題名 | |
| 内容 | |
| 投稿者 | |
| タイトル | |
| 投稿日時 | 2024年10月 |
2024年10月 優秀の裏に
日本の学生は世界的に見て優秀だといわれています。OECD(経済協力開発機構)の学力調査「OECD PISA 2022」で日本は加盟国37か国中、数学的リテラシー1位、科学的リテラシー1位、読解力2位ととても良い成績を示しています。この数字だけ見ると、今の学校の学習形態をなぜ変革していかなければいけないのかと疑問符が浮かびます。しかし、一方で、文部科学省・国立教育政策研究所の「OECD生徒の学習到達度調査 PISA2022のポイント」では、OECDでこれらの成績を出した生徒が「学校が再び休校になった場合、自律学習を行う自信はあるか?」といった質問に対して、「自信がない」と回答した生徒が日本は非常に多かったといいます。それがどれくらいかというと37加盟国中、なんと34位と下から数えた方が早いくらい少なったのです。つまり、自分から勉強する生徒が日本は極端に少なかったということが分かったのです。そのため、こういった傾向を受けて日本の教育において、「主体的・対話的な深い学びの視点からの授業改善」ということが言われるようになりました。
先日、門真市の教育委員会の方と、これから始まる門真市の小中一貫校「水桜学園」の教師の方々がたちばな幼稚園に見学に来られました。それと同時にこれからの主体的な学びに向けて、どのように幼稚園では保育を行っているかということを聞きに来られました。そこで、幼稚園の異年齢の話であったり、選択制の話やチーム保育という幼稚園で行っている藤森メソッド(見守る保育)の内容を紹介したのですが、その内容はこれから小学校で目指される内容に参考になる話であるといわれました。
「子どもたちが自ら学ぶ学習者になるにはどうしたらいいのか」ということが問われる教育現場になってきているのだろうと思います。そうでなければ、これから急激な変化が起きるといわれている社会に対応ができなくなる人材になってしまうと国は考えています。そして、これからの教育では「教える教育から環境を整える教育へ」変わるといわれています。この言葉は『個別最適な学び』と『協働的な学び』の一体的な充実を目指して」を著した奈須正裕氏が講演の中でお話しされていた言葉です。そこでも「適切な環境さえあれば、子どもは環境に関わり学んでいく。」といった「環境を通して行う教育」の重要性を話していました。これは私たちが使う認定こども園教育・保育要領でも「環境を通して」と書かれているように、乳幼児教育だけでなく、学校教育においても、環境づくりは非常に重要であることがわかります。
ただ、それ以上に大切なことは「子どもは自ら学ぶ力を持っている」と大人が子どもたちを信じることが何よりも大切です。そうでなければ、環境を整えることにも目は向きませんし、指導技術ばかりに目が向いてしまいます。今幼稚園で取り組んでいる藤森メソッド(見守る保育)の見守る三省には「子どもを丸ごと信じただろうか」という言葉があります。子ども以上に、大人の子どもに向けるまなざしこそ、今、問われているのかもしれません。
2024年10月6日