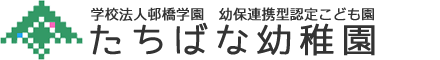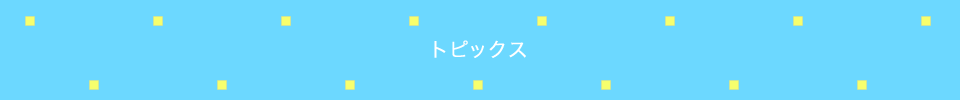| タイトル | |
|---|---|
| 内容 | |
| 投稿日時 | 2025年1月 |
明けましておめでとうございます。
新年あけましておめでとうございます。
保護者様に至りましてはいつも幼稚園の保育にご理解とご協力ありがとうございます。昨年は巻頭言にも書いたのですが、小学校との協力や年末には中国や韓国の先生方の見学など、外部とのつながりが多い年でした。今年はどのような年になるのか、ますます幼稚園の保育が発展していけるように頑張っていきたいと思います。
最近、保育者との会話のなかで私は「自由遊びこそが子どもの保育の中で優先順位が一番高いと思う」という話をします。それは自由遊びのほうが設定保育の中で先生中心で活動をするよりも子どもたちが自ら考える機会が多いからです。これまでの保育では保育者が子どもたちに様々な体験や経験をさせることが重要であるといわれていました。私もずっと保育とはそういったものだと思っていて、だからこそ、活動に子どもが向くように一生懸命に説明したり、楽しませる必要があると思っていました。しかし、その一方で、保育者が投げかける活動は保育者が大枠を作るのでそれほど子どもたちが考えるというよりは言われたことをすることが中心になります。制作においても、作るものは基本的には決まっていますし、子どもが自分で考える部分は色や描くものくらいの差しかありません。もちろん、子供の意見を聞きながら行うことで子どもの主体性を持たせることもありますが、それでも作る目的は決まっています。園によっては描くもの、書き方、色のしてすら設定されることがあります。そのため、作る過程に口を出すこともあります。一方で自由遊びは自ら作るものを選びますし、なにをしたいか、だれとしたいか、どうやって作りたいかからそもそも考えます。そこに大人の指示はなく、自ら何かしらを考えたり、友だちと関わらなければいけません。このように「0」から始まることが多いのが自由遊びです。まさしく、「自由」です。
では、設定保育は必要ないのかというと私はそうも思いません。子どもたちが自由に遊んだり、自分で考えて始めるためには「やってみたい」と思うモデルややれる環境がなければ何もできません。そもそも「どんなことができるのか」がわからなければ始めようとおもうことや挑戦しようと思うこともありません。つまり、私にとって設定保育とは「子どもたちが自由遊びで遊ぶためのきっかけやモデル、使い方のレクチャー」といったものになるように思います。だから、あくまで「優先順位」なのです。
これからの時代はこれまでのようにデータから打ち出されたアイデアをもとにした「1から2を作る能力」ではなく、「0から1を作る能力」のほうが重要視されていきます。その能力をつけるためには「自ら考える」「自らやってみようとする」「粘り強くやってみようとする力」が必要です。その力は決められた活動以上に自由に遊べる活動のほうが経験値としては大きいと思います。その際、大人がすることは子どもたちが「やりたいときにやりたいことができる環境」を用意することと「やってみたいと思う。興味関心をくすぐるためのきっかけ」を活動を通して多く用意することだと思っています。
先々、様々な問題やより複雑な問題が多くなるであろう日本社会で子どもたちがどういった力を今後必要とされるのか、そして、そのために幼稚園はどういった施設としてあるべきなのかを見通して2025年も保育を進めていきたいと思っています。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
2025年1月6日