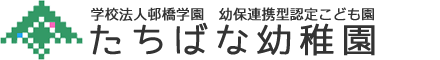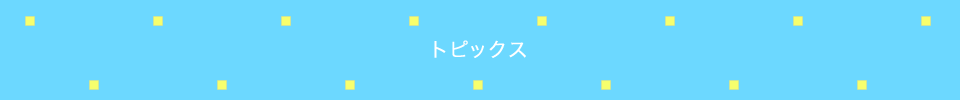| Number | 1 |
|---|---|
| 投稿年月日 | 2015年1月5日 |
| 題名 | 伝統 |
| 内容 | あけましておめでとうございます |
| 投稿者 | 副園長 |
2015年1月号 伝統
あけましておめでとうございます。新しい年の始まりですね。
今年はたちばな 幼稚園も認定子ども園に変わる年であり、たくさんの変化が起きる年になります。
とはいえ、子どもたちの成長発達をしっかりと保障するということはこれまで通り 変わらず、子どもたちの成長を見守っていくようにしていきたいと思います。
さて、お正月というと一年の中で日本の文化というものを実感できる瞬間ではない かと思います。新年を祝う行事であり、「初詣」や「おせち」「お雑煮」と日本の昔 からある習慣もまだまだ大切にされています。お正月を含め、ひな祭りや節分な ど、日本にはたくさんの年中行事があります。
保育をしていく中でもそういった年 中行事は年間のスケジュールの中に組み込まれています。ではなぜ、そもそも年中 行事はあるのでしょうか。
年中行事は暦に基づいています。そして、もともと暦は中国から奈良時代に日本に 来ます。中国では、奇数は偶数で割れない数字(固い、割れない、分かれない、に 通じる)であることから良いことをあらわす「陽数」と考えられ、神聖なるもの・ 無限なるもの・偉大なるものを意味し、縁起のよいものとして愛用されてきまし た。逆に 偶数は「陰数」と考えられ、嫌う思想がありました。また、この陽の数 が重なる日を大切な節目と考え、「節」といいます。そして、唐時代の中国の暦法 で定められた季節の変わり目のことでもあります。しかし、奇数が重なると合わせ ると偶数になり、陰数になってしまいます。
なので、中国ではその邪気を払うため 季節の旬の植物から生命力をもらい邪気を祓うという目的とした行事が行われ、日 本ではその中国の暦と日本の農耕を行う人々の風習が合わさり、定められた日に宮 中で邪気を祓う宴会が催されるようになり「節句」といわれるようになったそうで す。
そして、この「節」という季節の節目に、稲作を中心とした日本では、季節を感じ 心豊かに暮らせること、体調を崩しやすい季節の変わり目に「無病息災」を願い豊 作、健康、子孫繁栄を人々が神に祈り食物を供え、祝う行事になりました。
だから、日本の行事は「1月1日」「3月3日」「7月7日」など奇数月で奇数の日 が多いのですね。しかし本来は、5月と9月にも行事があり、「五節句」と言われ ていました。ですが、明治 6 年に廃止され、正月(1月)・桃の節句(3月)・七夕 (7月)が現在でも定着して残っているそうです。
子どもたちにとっては、行事というのはとても楽しいもので、毎回楽しみにしてい ることが多いと思います。しかし、その中には日本の大切な文化や習慣があるので す。こういったことを子どもたちに伝えることや感じてもらうことは今後のグロー バルな社会にはもっと必要なことかもしれません。一つ一つの保育の中にしっかり と意図をもったことを深めていけるよう考えていきたいと思います
2015年1月5日