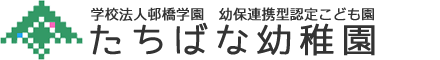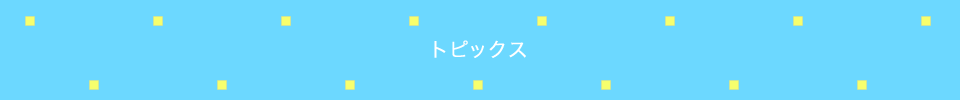| タイトル | |
|---|---|
| 内容 | |
| 投稿日時 |
8月巻頭言 描く手と、信じるまなざし
先日、大阪・関西万博に、幼稚園から出展協力させていただいた絵を見に行ってきました。園のInstagramでも紹介しましたが、今回一緒に作品づくりをしたのは、寝屋川出身のパラアーティスト・MUSASHIくんです。彼は知的障害を持ちながら、自由な感性と豊かな色彩で数々の作品を生み出してきた若きアーティストです。園内を見学し、そのイメージをもとに描いてくれた4枚の絵からは、彼ならではの世界が広がっていました。
MUSASHIくんが今のように自由に表現できるようになった背景には、周囲の人々のまなざしがあります。たとえば、通っていた絵画教室の先生は、彼が好きな画材や表現方法を自由に使えるようにしてくれたそうです。本人の感性を尊重し、枠にはめずに見守ってくれたことが、彼の可能性を広げる原動力になったのだと思います。また、今回の万博への出展やコラボレーションを支えてくださったプロデュースの方々との出会いも、彼の表現を社会とつなぐ大きなきっかけになったことでしょう。
このように、ありのままを信じて関わり、その人の力を引き出す環境づくりは、保育の中でも通じることだと感じました。私たちが日々実践している藤森メソッド(見守る保育)には、「見守る三省」という保育者の姿勢を省みる問いがあります。一つ目は、「子どもを丸ごと信じただろうか」。子どもは無知な存在ではなく、自ら育とうとする能動的な存在であるという認識が出発点です。二つ目は、「子どもに真心をもって接しただろうか」。子どもだからと軽く扱うのではなく、ひとりの人間として向き合えていたかを問います。そして三つ目は、「見守ることができただろうか」。これは、ただ見ているのではなく、理解し、認め、ともに生きる姿勢を意味します。
最近では「ダイバーシティ(多様性)」という言葉をよく耳にします。年齢、性別、価値観、障がいなどの違いを受け入れ、それぞれの力を活かす社会を目指すという考え方です。けれど、子どもたちを取り巻く現実にはまだ課題があります。「意見表明の権利」「貧困」「いじめ」など、日本は国連から複数の勧告を受けています(※2019年時点)。子どもの声が届きにくい社会だということが示されているのです。
私はその一因として、「子どもの自由度の少なさ」があるように感じています。自由がなければ、子どもは自ら考え、選ぶ力を育てることができません。ただし、ここで言う「自由」とは、好き勝手にしてよいという意味ではなく、大人が用意した枠組みの中で、子どもたちが安心して自己発揮できる自由です。その「枠」をつくるのが、大人の役割です。だからこそ、保育の中で「選択」という関わりはとても大切です。子どもには選ぶ力があります。その力を信じて任せるには、まず私たち大人が信じ、支えることが求められます。
MUSASHIくんのように、自分の表現を信じて進む人が育つ社会を目指して。私たちも日々の保育の中で、子どもたちの可能性を信じるまなざしを持ち続けたいと思います
2025年8月7日