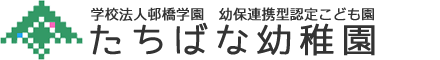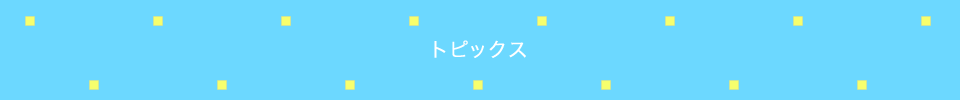| タイトル | |
|---|---|
| 内容 | |
| 投稿日時 |
入試やテストの変革
2025年4月15日の日本経済新聞に「学力テストPC本格導入」という記事がありました。これは小中学生を対象に毎年行われている全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)でパソコンを使ったオンラインで回答する試験(CBT)が本格導入されたという記事です。CBTはコンピューター・ベースド・テスティングの略称であり、今回は中学理科に導入されて、ほかの教科はこれまで同様紙での実施になるそうです。2026年度は中学英語での導入になり、27年度には神の問題はすべて廃止する予定となっているそうです。
CBTでテストを行う大きなメリットは問題の幅が広がるということだそうで、動画を利用して道具の適切な使用方法を選んだり、図を移動して電気回路を完成させるといった紙ではできない問題が出題できます。生徒は一人一台の学習用端末を利用して選択肢をクリックしたり、キーボードを使って文章を入力します。そして、各自の回答状況に応じて、大量の問題のセットから難易度や種類の違う問題を出すといったIRT(項目反応理論)方式によってその児童自身の学力にあったテストの出題と判定が行われるようになってきます。つまり、どの難易度の問題を安定的に正答したかをAIが自動採点し結果を測ることで、全員が同じ問題を解く紙方式よりも、児童の学力を詳細に把握できることができるようになるのです。これまでのような「運」での正答以上により詳細に理解度がわかるということにもなりそうですね。また、問題は一部を除いて非公開となり、同じ問題を何度も出すことができます。そのため、学力の変化や理解度の変化も測定できるようになってきます。何よりも、パソコンでの回答のため、学校外からでも受けられるというメリットもあり、不登校や病気療養中の児童生徒が参加しやすいですし、回答の回収や採点の手間といった運用面でのメリットも大きいことがあげられます。
このCBTはフランスの学力調査や経済協力機構(OECD)の学習到達度調査(PISA)などでも活用されており、国際標準にもなりつつあるようです。このようなことに日本は世界的に見てもかなり遅れを取っていますが、こういった全国規模のテストで検証を積み重ねることで、大学入試やほかの学力試験、資格試験などへの拡大につながる可能性があると記事にはありました。今後は大学入学共通テストでの導入も検討されていたり、佐賀大は18年度の推薦入試から大学入試でタブレットを使った試験が実施されています。司法試験でも26年からCBTへ切り替わる予定だそうです。
これからの入試であったり、試験であったりはこういった形式に確実に変わることが紹介されていました。この手の話を聞くと「カンニング」が話題によく取り上げられますが、この方法であると、その対象児に合わせた出題がAIによって出題されるので、カンニングする意味が無くなってきます。相対的な評価からより絶対的な評価になる分、一人一人の学力をより詳細に見えるようになってくるようになってきます。そもそも、PCを利用しての試験なので、ツールを使って解答するため、カンニングというもの自体の概念も無くなってくるかもしれません。絶対評価になってくるのはとてもいいことだと思います。これまで「勉強がわからない」といった子どもたちは落ちこぼれていくような年齢別の教育から、それぞれの理解度にあった教育を受ける足掛かりにもなるように思います。
私は常々、義務教育は本来「義務教育期間に学ぶことを習得する義務」が求められることに対して、今の日本の義務教育は「在籍する義務」になっているように思えてなりません。だから、「落ちこぼれ」や「吹きこぼれ」(高い学力や旺盛な学習意欲を持つ児童や生徒が通常の学校の授業に物足りなさを感じてしまうという現象)といった問題が起きているのだと思います。最近では「個別最適な学び」や「協働的な学び」ということが言われています。まさにその足掛かりとして、今回の記事はそこに向けた試験や入試の変化に感じます。教育は日本を挙げて大きく変革が行われているということを感じます。
2025年4月16日