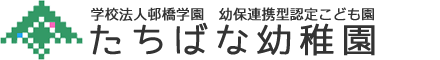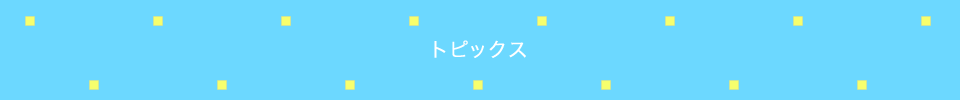| タイトル | |
|---|---|
| 内容 | |
| 投稿日時 |
AIとどう向き合う?
新年度が始まりました。入園式も終わり、乳児クラスには預かり保育の子どもたちが来るようになりました。幼児クラスは始業式が始まるまで、少しゆったりとした時間が過ごしています。この始業式の時間を利用し、職員研修をしています。特に年度の初めは幼稚園の大きな目標とこれから必要とされる能力、未来に向けて今幼稚園は何をする必要があるのかといったコンセプトのようなものを話すようにしています。特に昨今は生成AIの発展が顕著ですね。ソフトバンクの孫正義さんがテレビ番組で「今後12年で10億倍、今のAIから発展する」と話されていました。トランプ大統領がアメリカで就任した後にトランプ氏と孫氏が並んで、AI事業のニュースになっているのを見ると、「これは本当に怒るのかもしれないな」と思ってしまいます。このことについて、どう思いますか?私は楽しくもあり、怖くもあるというのが正直なところです。ただ、時代は待ってはくれませんし、12年後と考えて、今年入園した0才児の子どもたちは12~13歳ですし、年長さんでも、17~18歳です。ということは、社会に出るころにはいったいどれくらい進化しているのかと考えてしまいます。
そんなことを思っている中、東洋経済オンラインの2月6日の記事に「東大生があえて『ChatGPT』を課題で使う納得の訳。宿題で使うのはアリ?教育とAIの向き合い方」という記事がありました。実に興味深い内容です。この記事の元は東大カルペ・ディエムの西岡壱誠さんの話をまとめたものです。そこには多くの学校の先生が「読書感想文や調べ物のワーク・宿題をする際、生成AIを使ってしまうので困っている」という話があったそうです。そのため、学校でもChatGPTを全面禁止する学校もあり、生徒からそれについての反論があったりするそうです。しかし、一方で、東大生も高校時代の宿題や、大学の課題をこなす際にChatGPTを使っているそうです。その内容を見るととても考えさせられます。
東大生は課題にAIを使う際、課題を解く一番最初の段階で、ChatGPTを使うそうです。そうすると解答の例を提示してくるのですが、その内容は無駄が多くあったり、調べが甘いものです。そのため、無駄な部分はカットし、整理します。こう見るとChatGPTなどのAIも完ぺきではありません。西岡さんは「ChatGPTは論理的で完全に正しい文章を出すのは難しい」と言っています。膨大な量の文章データから「こういった質問が出ると、こう答えるパターンが多い」と判断して回答しているだけなので、整合性がとれていない回答も出力されるのです。つまり「答えらしいもの」になるなるわけです。
つまり、東大生は曖昧な内容に整合性を与え、ChatGPTを基盤として、人の手で調べることで課題を作っていたのです。すべてを頼るのではなく、裏付けを取ったり、その内容を深堀りしていくという作業をしていかなければなりません。そう考えると、ChatGPTを使ったといえど、内容のことは理解していなければいけません。あくまで「たたき台」を作ってもらうことをAIに頼っているだけなので、それだけではいけないのです。しかし、AIを使うことで、自分の調べる時間を短縮することや頭の整理、内容の骨子ができます。あくまで、「自分で考えるためのツール」として使うことで教育でChatGPTを使うデメリットは消えると話しています。ChatGPTを使うことのデメリットは「自分で考えなくなること」です。あくまで、頭を整理するためや骨子の部分をつくために使うのであれば十分勉強の役に立つといえると話しています。
私たちはAIを怖いものと考えてしまうのは、AIに対して、「すべてをまかそう」としているからかもしれません。うまく使い、うまく利用することでよりよい社会を作ることができるツールとして共存し、使っていかなければいけないのだろうと思います。これからの受験でも生成AIを利用するような試験にかわってくるかもしれません。その時に必要な力は「AIを使える力」ではなく、「どのようにして使うか」というスキルが求められてくるというのを今回の内容でも感じました。保守的に考えていても、時代はどんどん進化していきます。その進化を生かしていかなければ社会でもビジネスでも乗り遅れてしまいます。そして、その根本となる柔軟な頭の使い方を育てるのは乳幼児期の遊びにあると思っています。教育現場や保育現場はもう少し、こういったことを知り、今のを見つめなおす必要があるように思います。
2025年4月2日